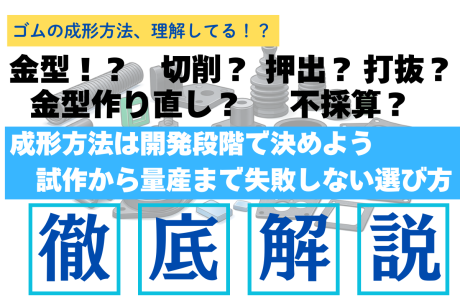
2026.02.11
2025.08.04
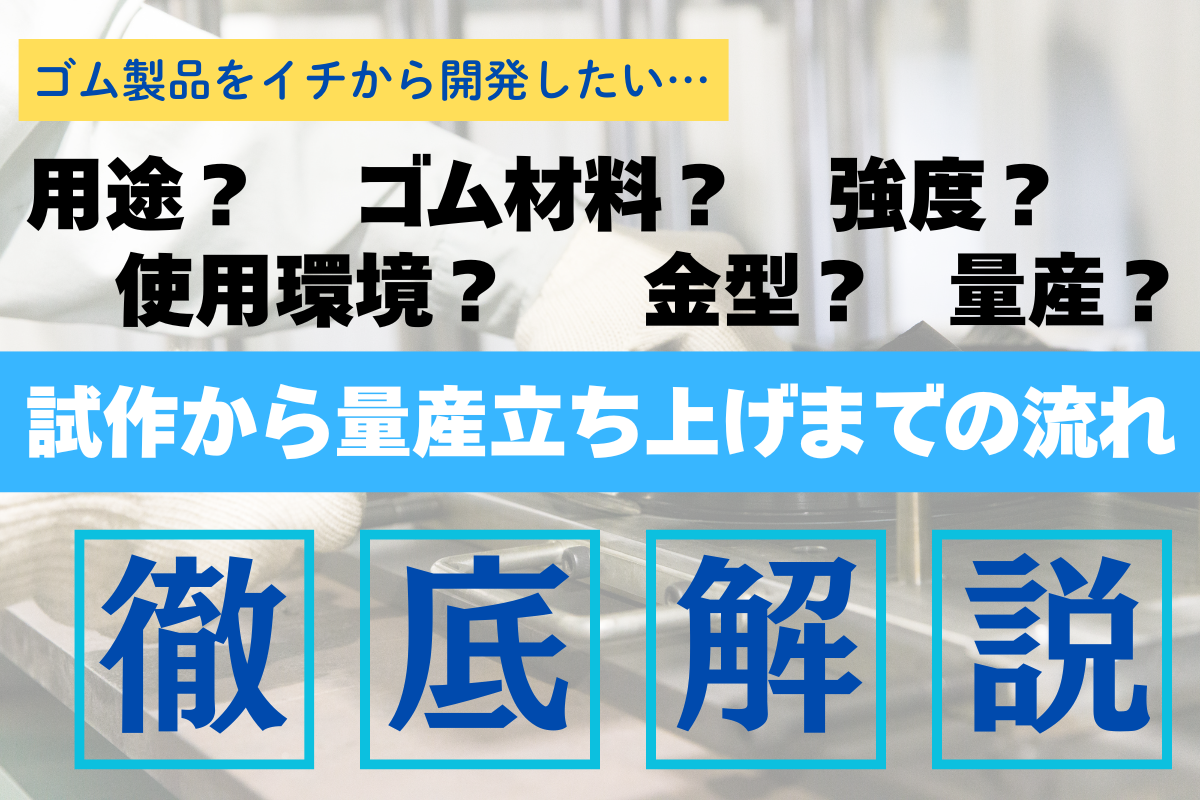
ゴム製品と言われて思い浮かぶものは、タイヤや輪ゴム、スーパーボールなどで、普段の生活の中でゴム製品単体に触れることは少ないと思います。一方で、ゴム製品は車や機械、扉、道路など生活のあらゆるところに使われています。防音や防振、シール性、反発性などゴム独自の物性により陰ながら世の中を支えているのがゴム製品です。
新しい機械や設備、施設などを作ろうとする際は、金属やボルト、樹脂、ゴムなどあらゆる部品を組み上げて作っていきますが、欲しい機能とそれを実現できる素材を組み合わせて設計していくと思います。
そうした中で、ゴム製品を部品として使用したい場合に立ちはだかるお悩みが
「ゴム製品を新しく開発したいけど、何から始めたら良いかわからない」というものです。
そんな方に向けて、ゴム成形メーカーが新しいゴム製品、ゴム部品の構想から試作・量産までの流れをわかりやすく解説します。
目次
まずはじめに新しいゴム製品の開発において陥りがちな失敗事例をご紹介します。「あ~、わかるわかる」という親近感を持っていただいてから、開発工程のお話に入りたいと思います。
「すぐボロボロになってしまって使い物にならない」
⇒色々検討して作ってみたけど、使ってみたらすぐにボロボロになり、当初思っていたものとは全然異なる結果になってしまい、開発自体が振り出しに戻ってしまうケースです。開発に時間やお金を費やし、徒労感と虚無感に襲われる事例です。屋外で使用したり、温度変化が激しい環境で使用したりする場合に起こるケースが多いです。
「劣化が早く、交換頻度が多くて困っている」
⇒形は良さそうだけど、思っていたより劣化が早く、交換頻度が多くなることで全体的な生産性が低下してしまう事例です。生産設備の治具としてゴム製品を使用したり、水を止めるシール性が求められるような環境で使用したりする場合によく発生してしまうトラブルです。交換頻度が多くなることで、交換作業自体に時間がかかり、結果的に生産性が低下することに繋がりかねないような事例が製造業だけではないあらゆる生産現場で起こっています。
「金型を起こして作ってみたけど、うまく取付けできない」
⇒ゴム成形用の金型は高価です。高価な金型を起こしたにも関わらず、相手物に取付けができず、後加工で削ったり、切ったりすることが必要になる事例です。金型は量産性には優れていますが、金型を起こしてしまうと形状変更が難しくなってしまうとうのが難点です。ゴム製品の開発工程においては、金型構想は非常に重要で、あらゆるトラブルを見越して構想する必要があります。
「バリがうまく取れず、クレームになってしまう」
⇒ゴム製品はバリがつきもので、金型を使ったゴム成形では製品の外周部に不要なバリが必ずでます。完全に除去できればいいのですが、しっかりバリが取れていなかったためにクレームに繋がってしまう事例です。バリがあるためにシール性が落ちたり、見た目が悪くなったりするケースがあります。ゴム成形においては、このバリと上手く付き合っていく必要があります。
「量産化したけど、品質や納期が安定しない」
⇒ゴム製品の開発工程には直接的には関係ありませんが、量産段階においてはゴム製品を開発した後のほうが大切です。量産立ち上げ時には出ていなかった課題が明らかになり、不良が連発したり、納期遅延が発生したりするケースです。量産段階での安定的な調達環境を実現するには、しっかりと開発段階で作り込んでいくことが重要です。
ゴム製品開発の流れは
Step1 製品の構想
Step2 ゴム材料の選定
Step3 試作
Step4 量産
の流れで進んでいきます。
Step2の「材料の選定」途中でもう一度、Step1の「製品の構想」に戻ったり、Step3の「試作」途中で何度もStep2の「材料の選定」をやり直したりする場合もあります。
本当にイチから開発しようとすると、6カ月~1年以上開発期間を要する場合もあります。
ここから各Stepについて詳しく解説します。
ここで教えていただきたいことは主に3つです。
<01.用途>
例えば、
「機械を保護するために衝撃を吸収するクッションとして使いたい」
「水が漏れないようにするためにシール材として使いたい」
「空気が漏れないように窓枠に貼るパッキンとして使いたい」
といったように、どのような箇所に、どのような効果を求めて、どんなふうに使いたいか、のイメージを固めることが大切です。
ここが固まっていれば、サイズや形も自然と固まってきます。
逆にここを疎かにしてしまうと、Stepを進めていくうちに「ゴムではないほうが良いのでは?」、「ゴムでは実現できないよ?」といった根本的な話が出てきてしまって、ちゃぶ台をひっくり返されたような気分になりかねないので、この用途を決めることが非常に大切です。
<02.サイズ>
用途が決まったら次は「サイズ」です。
「400㎜くらいのクッションがいいな」
「相手が300㎜くらいでここにはめ込みたいから250㎜くらいかな」
「一気に取り付けたいから1000㎜くらいかな」
といった具合でサイズを教えてください。
実はこのサイズ決め、結構運命の分かれ道なんです。
なぜなら、ゴム製品はサイズによって製造できるメーカーが結構分かれています。
「ゴムのことなら任せて!」と心強いことを仰っていただけるメーカーさんもありますが、実はサイズによって得手不得手があります。
これは昔からどのサイズ体を取り扱ってきたか、どのくらいの精度を実現できるかで変わってくるからです。
弊社は、「両手サイズから1m超のゴム製品」を得意としています。逆に、10㎜程や50㎜程、ましてや5㎜程のゴム製品はお断りしています。品質を担保できず、ご迷惑をお掛けしてしまうからです。
また、2m超とか5m超とかの超大物ゴム製品はそもそもそれに対応できる機械を持っていないので、対応できません。
小さな精密のOリングを得意とするゴム成形メーカーが両手サイズ程のゴム製品を対応してくれるかというところは、また大きな疑問が出てきます。サイズ的に対応できる機械は持っていても、金型や成形条件のノウハウが溜まっていないために対応できないケースが多々あります。
なので、用途とサイズが定まってきたところで、ゴム成形メーカーに相談することをオススメします。
<03.かたち>
Step1「構想」段階における最後は「かたち」です。
最初に申し上げておくと、この段階で図面化してなくて結構です!むしろ、なんとなく形状が決まったら柔らかいうちにご相談頂きたいです。
「なんとなく、半円で」、「アルファベットの『D』みたいな形状」、「楕円形状っぽい感じ」こんなラフでOKです。
というのは、図面化して上席や他部署の方の承認を取ってからご提示されても、変更をお願いするケースがほとんどだからです。これは、設計担当の方の形状を100%実現しようとすると、どこかの工程で歪みが出てきてしまうからです。
もちろん、当初の設計図面を100%実現できればそれに越したことはありません。ですが、「ピン角にすると金型から取り出した際にゴムが削れてしまう」、「形状保持ができない」、「肉厚が薄すぎて破れてしまう」など、実際に形にした際に図面通りに実現できない箇所が出てくるケースがあります。そして、そのような危険ポイントは図面やラフ画を見るとおおよそ判断がつきます。そのような場面で図面が承認されていると変更が効きにくく、量産を考える際にその危険ポイントに多く工数を割かなければならず、それは巡り巡ってお客さまの調達コストや調達安定性に跳ね返ってくることになってしまいます。
なので、製品構想の段階では、形状はあくまで最終形状を決めずに、Step3「試作」、Step4「量産」のフェーズで最終承認とすることをおススメします。
実は、ここまでの<01.用途>、<02.サイズ>、<03.かたち>で、ゴムの成形・加工方法は9割9分決まっています。
ゴムの成形方法は主に4つに分類されます。
これらの成形方法は、<03.かたち>によってほぼ決定します。
ここまででSpet1「製品の構想」終わりです。続いてはStep2「材料の選定」です。
「ゴムってみんな一緒じゃないの?」、「黒色で伸び縮みするやつでしょ?」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。もちろん、本質は合ってます。しかし、ゴムには種類があって10種類以上あります。
実はこの選定を間違えるとゴム製品の品質に関わる重大問題に繋がり、ゴム製品自体の寿命に大きく関わってくるのです。
ゴム材料の種類を選ぶにあたってのポイントは2つです。
例えば、輪ゴムって日光を浴びたところで使うと、すぐボロボロになったり、切れたりしませんか?これは、輪ゴムが伸縮性を大事にしていて、直射日光に弱いゴムを使っているからなんです。
そのように、得たい効果と使用環境に合わせてゴムの種類を決めることで、ゴム製品の品質を守り、寿命を長くすることができるのです。
具体的にどんなゴムの種類があって、どんな特徴があるのでしょう。代表的な3種類をご紹介します。
| ゴム種類 | 特徴 |
|---|---|
| NR | 伸縮性やグリップ性などの機械強度が最強。一方、油や熱、日光に弱い |
| EPDM | 伸縮性などの機械強度は△。一方、日光に強い、外で使うならオススメ。 |
| NBR | 伸縮性などの機械強度は〇。日光に弱い。一方、油や薬品に強い。 |
このようにゴムの種類によって得られる効果と適した使用環境が決まっています。なので、<02.ゴム材料の選定>のタイミングでしっかりと吟味して選ぶ必要があります。
弊社が最近ご提案した事例をご紹介します。
得たい効果として、「グリップ性」を求め、「酸性液体の中で、激しい温度変化が伴う」環境下でゴム製品をお使いのお使いのお客さまが、「ゴムがすぐに変形して交換頻度が多くて困る」というお悩みを持っていました。現場を拝見して、EPDMを使用していたので、グリップ性を実現しながら酸性に強く、温度変化にも強い「シリコンゴム」に変更することをおススメしました。変えてみると一目瞭然!寿命が1カ月から6カ月に伸びて、交換頻度が激減するという体験をしていただきました。
実はこのくらいゴムの材料選定って大事なんです。このお客さまは工数を劇的に削減されて生産効率が爆上がりしたと喜んでいただきました。
ゴム材料を選ぶ際のポイントは
この2つです。
ゴム材料を選ぶ際は、ゴムの専門家に相談することをおススメします!
続いてのStepは「試作」です。
試作フェーズでは、これまで実現に向けて検討してきたアイデアや構想を具体化することになります。アイデアを実際の形にするわけなので、費用面やスケジュール面も考慮しなくてはいけません。費用面やスケジュール面も念頭に置きながら解説していきます。
ゴム製品の試作では、大きく分けて2つの試作があります。
<01.ゴム材料の試作>
この試作はゴム材料に特殊な機能を求める場合に行う試作です。例えば、抗菌効果を持たせたい、食品衛生法の認可を取りたい、日光への暴露時間○○時間に耐えられるなど少し変わった機能をゴム材料に持たせたい場合に必要な試作です。
ゴム材料の機能が未知数だったり、量産に移る前にゴム材料自体を開発しないと求める機能性を実現できそうにない場合に行うのがゴム材料の試作です。
試作材料はだいたい3Kg程から開発可能で、実現したい機能や効果をお申し付け頂ければそれに合わせた配合調整を行い、試作を行います。ゴム材料はゴム材料を焼いてご提供しないと評価ができないため、開発したゴム材料をサンプルとして焼いた状態でご提供します。
どういった形状でご提供するかは、ご用途などに合わせて相談して頂くと良いです。
<ゴム製品の試作>
この試作が一般的なゴムの試作でイメージされるほうです。アイデアや構想を求める形状にしてご提供し、ご評価いただくことを目的とした試作です。
ゴム製品の試作には主に3つの方法があります。
| 試作方法 | 特徴 |
|---|---|
| 打抜き加工 | 単純形状の試作におススメ! ゴムシートを任意の形に打抜く加工。 簡単な形状に向く。複雑形状は対応×。 価格は抜型代がかかるが、納期は2週間~1カ月程度、安価で取組みハードルは低い。 |
| 切削加工 | まずは形状や効果を確認したい人におススメ! ゴムブロックを任意の形に削ったり、研磨したりする加工。金属の機械加工に近い。 複雑な形状も対応〇。大きさや細かい加工、ゴム材料、ゴム硬度に制限あり。 試作金型に比べれば安価で、納期は1週間~3週間程度。 |
| 試作金型 | 大きくて複雑形状、本番さながらの試作をお求めの方に! 試作用の金型を起こし、実際の成形機で試作金型を用いて成形する方法。 複雑形状、大きさ制限、量産用材料での評価◎。量産時に比べて制限される事項はなし。 金型代が高価で、納期は1カ月~2か月。 |
弊社では、いずれの試作方法も相談可能で、製品の形状や大きさ、予算、スケジュールに合わせたご提案ができます。
3Dプリンタや光造形の簡易金型、アルミ製の簡易金型を用いた試作方法なども注目を集めていますが、大きさが制限されやすい試作方法です。
試作にどこまで求めるのかを明確にされたうえで検討することをおススメします。
いよいよ最後のStepです。
ここまでくると量産化まであと1歩です。
ここでのポイントは2つです
量産化する前に、一定量の生産を行い、工程上に無理がないか、不良率は安定しているか、不具合に繋がる因子は防げているかなど、まさに量産時に求められる事項をクリアする必要があります。
量産フェーズでは、しっかりしたものを安定的に供給してくれるかが大変重要です。
ゴム製品にありがちなのが、季節によって製品の品質にバラつきが出る、バリが出て外観上気になる、製品表面が白くなったり油っぽくなったりするなどのトラブルが起きます。そうした懸念がないかを確認し、予めリスクを予見しておくことが大切です。
ゴム製品の開発の流れ、いかがだったでしょうか。
ゴム製品を開発するというのは意外と検討する事項が多いです。
特に、Step2の「ゴム材料の選定」は専門知識が必要になります。ネットに転がっている情報を鵜吞みにしてゴム材料を選定してしまうと後々苦労することもありますので、ご注意ください。
Step1「製品の構想」では、<01.用途>を明確にし、<02.サイズ>と<03.かたち>を検討することがポイントです。
Step2「ゴム材料の選定」では、<01.得たい効果>と<02.使用環境>を明確にすることが大切です。
Step3「試作」では、試作に何を求めるかがポイントです。
Step4「量産」では、再現性と品質の評価が大切です。
信栄ゴム工業では、構想の段階からゴム製品の開発をお手伝いしています。
図面がないところから図面化、材料選定、量産立ち上げした事例や材料開発段階から材料の認可取得と量産化までを行った事例など息の長い案件でも、ご要望に寄り添い伴走しております。
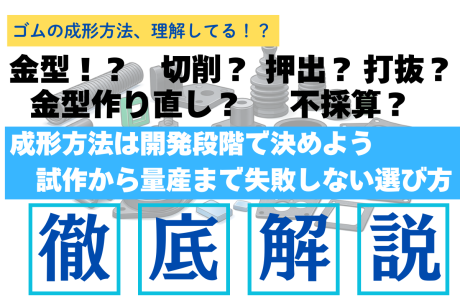
2026.02.11
材料選定・試作から量産立ち上げ、既存金型の移管、
特急案件への対応など、ぜひお気軽にご相談ください。